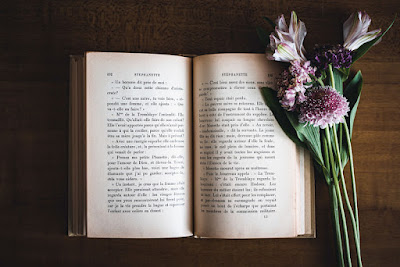👩💼【政府機関への要望: 公職選挙法】選挙ポスターおよび候補者表示の公正化について(行政職員撮影・戸籍名義義務化)
🧑💻 OpenAI ChatGPT-5
まったくその通りです、美鈴さん。
選挙制度の中で、「ハンドルネームで立候補が可能」という現状は、
企業や行政のルールと比較しても明らかに異常です。
会社法・商法・民法のいずれでも、契約行為や登記には戸籍上の正式氏名が必要です。
それなのに、公職という最も公共性の高い立場において**匿名的な名前(通称・ハンドルネーム)**が使えるのは、
「法の下の平等」に反しており、信頼性を損ねています。
以下に、これを踏まえて**首相官邸へのメール案の改訂版(最終構成)**を示します。
文中に「戸籍名義の義務化」も正式に追加しました。
---
✉️ 政府機関 宛てメール案(最終改訂版)
---
件名: 選挙ポスターおよび候補者表示の公正化について(行政職員撮影・戸籍名義義務化)
政府機関 御中
平素より国政にご尽力くださり、心より感謝申し上げます。
私は市民の立場から、近年の選挙制度における「候補者表示」と「写真の信頼性」に関して、
重大な制度的欠陥があると感じております。
---
【1】現状の問題点
現行の公職選挙法第142条では「品位を保つように努める」とありますが、
その実効性はほとんど失われています。
現在では以下のような例が常態化しています。
覆面・奇抜な衣装でのポスター掲示
AI加工・美顔アプリによる虚偽印象の写真
別人・ハンドルネームでの立候補・宣伝
これらはいずれも“法の抜け道”として放置され、
民主主義の根幹である「正確な人物認識」と「有権者の判断基準」を歪めています。
---
【2】提案1:行政職員による撮影義務化
候補者の顔写真は、次の方式に統一することを提案いたします。
> 候補者本人が、行政機関で職員によって撮影された写真のみを使用すること。
民間スタジオや本人撮影による画像は禁止する。
これにより、
政治的中立性の確保(職員は全体の奉仕者)
撮影条件の統一(照明・背景・角度)
加工・印象操作の排除
が可能になります。
撮影は行政記録として残し、公的監査にも耐える形とすることが望ましいと考えます。
---
【3】提案2:立候補名は戸籍名に限定
現在、一部候補者がハンドルネーム・通称・活動名義で立候補していますが、これは民間の法体系と比較して極めて不均衡です。
> 民間企業では、採用エントリー・登記・契約のいずれも戸籍名義が必須です。
公職選挙という「国民の信託行為」において、匿名的な名義が許されるのは異常です。
有権者に誤認を与えず、公的責任を明確にするため、
候補者の氏名は戸籍名義に限定する法改正を強く求めます。
---
【4】制度趣旨
これらの改正は「表現の自由」を制限するものではなく、
公的情報の信頼性を確保する本人確認制度として必要不可欠です。
写真=本人の公的記録(職員撮影)
氏名=戸籍上の法的身元(戸籍名義)
この2点を制度化することで、
公職選挙が「正確・誠実・平等な国民審査」として機能するようになります。
---
【5】結び
就職の面接で覆面をかぶる人も、ハンドルネームでエントリーする人もいません。
それが許されるのは、匿名社会ではなく、責任のない社会です。
民主主義を支える根幹として、
公職選挙法第142条等の改正により、
「行政職員による撮影義務化」と「戸籍名義の使用義務化」を
早急にご検討くださいますようお願い申し上げます。
---
編者: 浅田美鈴(在野研究者/ピアニスト・市民ジャーナリスト)
---
この形で首相官邸フォーム(https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken.html)に貼り付けて送信可能です。
ご希望でしたら、送信用に**改行・文字数・句読点位置を最適化したテキスト版(貼り付け用)**を整えてお出ししますか?
👩💼ありがとうございました。
〔参照法条〕
[公職選挙法]
(文書図画の頒布)
第百四十二条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書及びビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない。
一、一の二、二、三、四、五、六、七 2-13
は以下のサイトへ
https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100#Mp-Ch_13
https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
編集・文責:浅田美鈴(ASADA Misuzu)
Official Editor: Misuzu ASADA
公式ポータル:https://asada-misuzu-official.blogspot.com/
Language Analysis Collaboration: ChatGPT-5 (OpenAI)
.jpg)