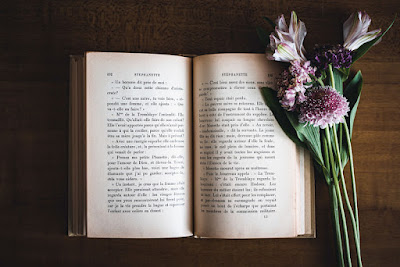💴💵💶 ▓ 6 予算ーーー財政民主主義の具体化(3)-(1) 財政ーーーーーフォーラム13
(1) 予算の法的性質のとらえ方には古くから争いがある 【Gemini】 憲法86条と予算について 憲法86条は、内閣が毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して審議と議決を経なければならないと定めています。これは、国民の代表である国会が国の予算を最終的に決定し、財政民主主義を実現するための重要な規定です。 簡単に言うと * 内閣が予算を作る: 国の1年間の支出計画を政府が立てます。 * 国会が審議・議決: 国会が予算案を詳しく検討し、最終的にOKを出すか決めます。 * 国民の代表である国会が決定: 国民の代表である国会議員が、国民の税金の使い方を決めるということです。 なぜ憲法に規定されているの? * 財政民主主義: 国民の代表である国会が予算を決定することで、国民の意向が反映されるようにするためです。 * 権力分立: 政府の権力を制限し、議会がチェック機能を果たすためです。 もう少し詳しく * 予算の種類: 一般会計予算、特別会計予算など、様々な種類の予算があります。 * 予算の手続き: 政府が予算案を作成し、国会に提出、各委員会で審議、本会議で議決、という流れが一般的です。 * 予備費: 予期せぬ事態に備えて、一定額の予備費が設定されることがあります。 疑問点などあればお気軽にご質問ください。 例えば、以下のような質問はいかがでしょうか? * 予算が成立しない場合はどうなるのですか? * 予備費はどのように使われるのですか? * 予算と法律との関係は? あなたの知りたいことを教えていただければ、より詳しく説明できます。 関連キーワード: 憲法, 予算, 財政民主主義, 国会, 内閣 補足: この説明は、一般的な憲法86条の解釈に基づいたものです。より詳細な内容については、法学の専門書や、国会図書館などの資料をご参照ください。 https://gemini.google.com/?hl=ja [財政法] (a) 予算総則 (b) 歳入歳出予算 (c) 継続費 (d) 繰越明許費 (e) 国庫債務負担行為をもって予算とする(16条) 【Gemini】 財政法について 財政法は、国の財政に関する法律であり、予算の編成や執行に関するルールを定...